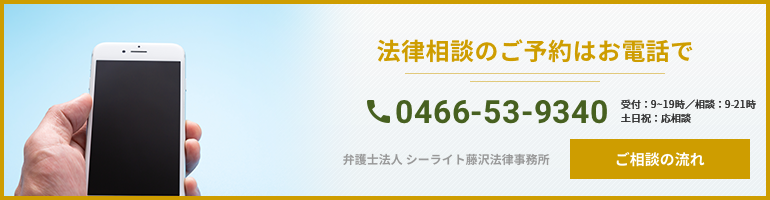育児休業者の処遇の変更は違法? 許されるケース・NG事例を解説

現代の日本社会において、性別に関係なく育児と仕事の両立ができる環境を整えることは重要な課題です。
その一環として、育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の法整備がされています。
そして、更なる育児・介護の支援に関する制度の充実化を目指し、2024年に国会で改正育児・介護休業法が可決され、2025年4月、10月に順次施行されます。
この育児・介護休業法では、さまざまな制度が設けられています。その制度の中には、育児休業制度や短時間勤務制度などがあります。
しかし、こうした制度を利用した従業員に対して適切な対応がなされず、結果的に処遇の変更が不利益と受け取られてしまうケースも見受けられます。そのような場合には、従業員との間でトラブルに発展し、訴訟などの法的トラブルに至ることもあります。
今回は、育児のため育児休業制度や短時間勤務制度を利用した従業員への対応として、許される処遇変更と許されない処遇変更(=法律で禁止される不利益取扱い)をどう区別していくかについて解説し、法的トラブルを防ぐポイントを紹介します。
Contents
育児・介護休業法の改正ポイント
育児・介護休業法は、労働者が子どもを養育したり家族を介護したりしながら働くことができるように、さまざまな制度を整備・提供しています。
そして、2024年には、より充実した支援を実現するために改正が行われました。具体的には、以下のような部分が改正されました。
育児に関するもので令和7年4月1日に施行された内容
子どもの看護休暇が小学校3年生まで拡大(改正法16条の2・16条の3)
子どもの看護休暇の対象となる、子どもの範囲および休暇の取得可能事由が、拡大されました。また、名称も子の看護等休暇に変更となっています。
対象となる子どもの範囲については、小学校就学前までから⼩学校3年生修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日)までに引き上げられています。
また、休暇を取得できる理由には、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほかに、感染症に伴う学級閉鎖や入園式、入学式、卒園式への参加などが新たに加わりました。
そして、労使協定に基づいて、継続雇用期間が6か月未満の労働者を看護等休暇の取得対象者から除外する規定を廃止しました。そのため、労使協定の締結により取得対象から除外できる労働者は、週の所定労働日数が2日以下の場合の労働者のみとなります。
所定外労働の制限(残業の免除)の対象が小学校就学前までに拡大(改正法16条の8)
2025年4月以降は、所定外労働の制限(残業の免除)を請求できる労働者が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子どもを養育する労働者までに広がりました。
短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加(改正法23条2項)
3歳未満の⼦どもを養育する労働者に関し、事業主が短時間勤務制度を認めることが困難な場合の代替措置として、テレワークの選択肢が追加されました。
※3歳未満の子どもを持つ労働者が短時間勤務を希望した場合、事業主側は勤務時間を6時間まで短縮しなければなりません。しかし、それを認めることが難しい場合の代替措置になります。
従来からの制度では、下記のような代替措置があります。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
- 時差出勤(始業・終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げ)
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
上記の措置に加え、新たにテレワークも選択肢に加わっています。
育児のためのテレワーク(改正法24条2項)
3歳未満の⼦どもを養育し、育児休業を取得しない労働者が、テレワークを選択できるよう、対応する事業主の努力義務が課されています。
育児休業取得状況の公表義務適用の事業主が拡大(改正法22条の2)
年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければならない対象事業主が、常時雇用する労働者数1,001人以上の事業主から常時雇用する労働者数301人以上の事業主まで対象事業主が広がりました。
常時雇用する労働者とは、雇用形態を問わず期間の定めなく雇用されている労働者のことになります。
たとえ期間の定めがあっても、過去1年以上引き続き雇用されている労働者や、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる労働者なども含まれます。
男性の育児休業等の取得率、または、育児休業等と育児目的休暇の取得率を、インターネットなどで公表することが義務付けられています。
育児に関するもので令和7年10月1日に施行される内容
育児のための措置(改正法23条の3第1項、第2項)
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの中から2つ以上の措置を選択し講じる必要があります。
1.始業時刻の変更(例:フレックスタイム制や時差出勤制度など)
2.テレワーク(10日以上/月)
3.保育施設の設置、運営
4.養育両⽴⽀援休暇の付与(10日以上/年)
5.育児短時間勤務
また、3歳未満の⼦どもを養育する労働者に対して、⼦どもが3歳になるまでの時期に、選択した上記制度に関する周知と制度利⽤の意向の確認を行う必要があります。(改正法23条の3第5項、第6項)。
妊娠・出産等の申出があった場合と、子どもが3歳になる前の個別の意向聴取(21条2項、23条の3第5項)
事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出たときと、子どもが3歳になる前の適切なタイミングで、勤務時間帯・勤務地等についての意向を個別に聴取する義務を負うようになります。
育児休業や短時間勤務制度を理由とした不利益取扱いの禁止
育児・介護休業法や男女雇用機会均等法では、妊娠・出産や育児休業、育児のための短時間勤務等を理由として不利益な取り扱いを行うことが禁止されています。
労働者が育児休業や短時間勤務等を利用し、またはその申出・取得を理由として、不利益な取扱いをしてはならないと厚生労働省がガイドラインで11項目の例を示しています。(法第10条、第23条など)
そのうちいくつか抜粋して紹介すると以下のとおりです。
イ 解雇すること
ロ 期間を定めて雇用される者について,契約の更新をしないこと
(中略)
ホ 自宅待機を命ずること
(中略)
ト 降格させること
チ 減給をし,又は賞与等において不利益な算定を行うこと
リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
ヌ 不利益な配置の変更を行うこと
ル 就業環境を害すること
これらの規定は、労働者の権利保護を目的としており、事業主には重大な責任が課されています。
処遇の変更は必ずしも不利益取扱いとはならない
では、短時間勤務制度を利用しているにもかかわらずフルタイム時と同じ給料を支払わないといけないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。
同じ給料を支払わないとならないのでは、短時間勤務制度を利用するとむしろ時間当たりの給料が増えるということになります。その結果、他の従業員の間で不公平感が生じ、モチベーションの低下や、職場内の人間関係の悪化を招くおそれがあります。
ですので、基本的には働いた時間分の給料を支払えば不利益な取り扱いにはあたりません。育児休業や短時間勤務制度の利用者を不利益に取り扱ってはならないとはいっても、処遇の変更をしてはならないというわけではないのです。
許される処遇の変更と許されない処遇の変更(法律上の不利益取扱い)とは
実務上の判断が難しいのは、「すべての処遇変更が禁止されているわけではない」という点です。処遇の変更内容と理由によっては、法的に許容される場合もあります。いくつかのケースを例に、法的に許容される処遇の変更なのかどうかを考えてみます。
Q1 フルタイムで9時-18時(1時間休憩)の8時間勤務をしていた従業員が、育児のため10時-14時(休憩なし)の短時間勤務となった場合、基本給を50%減額しても許されるでしょうか?
A. 働いていないことを働いていないと扱うこと自体は不利益取扱いではありません。8時間勤務が4時間勤務へと50%の就労時間になっているので、労働そのものの対価である基本給を50%減額すること自体は許されるものと考えられます。
Q2 Q1のケースで、その会社の業務の忙しいピークタイムが14時から17時という場合、時短勤務に切り替えた従業員が忙しい時間帯に業務ができないことを考慮して60%減額としても許されるのでしょうか?
A. 働いた時間分の給与を支払わないという不利益な取扱いになってしまう可能性が高いです。フルタイム勤務者との実質的な公平を図りたいという場合、多忙な時間帯の勤務者には特別手当を付けておき、この時間帯に勤務しない勤務者にはこの特別手当を支給しないというような形でバランスをとるべきです。
Q3 育児休業中の定期昇給を行わず、復職後の定期昇給を復職後の勤務実績のみを考慮して行うことは許されるでしょうか?
A. 育児休業前の勤務実績を考慮しないという意味で不利益な取扱いに該当する可能性が高いです。育児休業中の定期昇給を行わないこと自体は許されますが、休業前の勤務実績も加味して調整する必要があります。
Q4 8時間のフルタイムから6時間の短時間勤務制度の適用を受けている間の昇給幅を、減った勤務時間数を考慮して一律75%とすることは許されるでしょうか?
A. 基本給を8分の6に減額した上で、さらに昇給幅も8分の6とした事例について、不利益取扱いに該当し違法であると判示した裁判例があるので注意が必要です(東京地判H27.10.2)。
Q5 各種手当について,育児時短勤務者については,減った勤務時間分減額して支給することは許されるのでしょうか?
A. これは手当の性質によって違法か適法かの結論が変わると考えられます。例えば家族手当については遅刻・欠勤者を控除対象にしておらず、パートにもフルタイムと同額を支給しているという会社において、家族手当を減額してしまうと不利益取扱いに該当し違法となるでしょう。
育休制度だけでなく、他の社内制度とのバランスも考えなければなりません。
許される処遇の変更について
状況に応じて法的に許されると判断される場合のある処遇の変更についてまとめていきます。
- 勤務時間の短縮に応じた賃金の比例減額
時短勤務により実働時間が減るため、賃金が一定割合減額されるのは合理的です。 - 休職期間中の人事評価の停止
実際に勤務していない期間は評価対象外とすることは合理的ですが、復帰後の評価に不当な影響を及ぼすのは、いけません。 - 業務内容の一時的変更
育児と両立しやすい業務への変更が、本人の同意を得て行われる場合は、労働条件の合理的理由が存在するとして、有効と判断されることがあります。
ただし、上記のような事情に該当するか否かの判断は、非常に難易度が高いといえます。
なぜなら、表面上は、労働者が同意しているとしても、客観的に見て、労働者による納得した上での同意があると認められない場合には、違法な不利益取扱いに当たると判断される可能性があるからです。
許されない処遇の変更(法律上の不利益取扱い)について
一方、以下のような処遇の変更は、原則として違法とされる可能性が高くなります。
- 育児休業を理由とした解雇・雇止め
裁判例では、「育休取得予定を伝えた直後の雇止め」が違法とされた判例が多数あります。 - 人事評価・賞与の一律減額
育休中や時短勤務を理由に業績評価を下げるのは、能力や実績に無関係な不利益扱いとして違法と判断される可能性が高いです。 - 契約社員の更新拒否
契約更新のタイミングで育休を理由に雇止めするのは、不利益取り扱いに該当する可能性があります。
判例に見る実務の判断基準
社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会事件(東京地判平成27.10.2)
育児時短勤務制度を利用していた労働者が、通常勤務していた場合と比べ、労働時間数に比例した8分の6を乗じた号俸分しか昇給されませんでした。
これは、原告である労働者が被告会社に対して、昇給の抑制が育児介護休業法に違反する不利益取扱いであると主張して、損害賠償請求した事案です。
裁判所は、昇給抑制は、育児時短勤務制度の取得を理由として、労働時間が短いことによる基本給の減給(ノーワークノーペイの原則)のほかに、本来与えられるべき昇給の利益を不十分にしか与えないという形態により不利益取扱いをするものであり、育児介護休業法23条の2に違反する不利益取扱いに該当するとし、差額賃金及び慰謝料10万円の損害を認めました。
医療法人稲門会(いわくら病院)事件(大阪高判平成26.7.18)
被告法人では、定期昇給として本人給と職能給の昇給があるところ、育児休業規程において育児休業中は本人給のみの昇給とする旨を定めており、さらに3か月以上の育児休業を取得した場合には、その翌年度の定期昇給において職能給の昇給を行わない運用をしていました。
男性看護師である労働者は、3か月間の育児休業を取得したため、翌年度に職能給が昇給しませんでした。
また、男性看護師は、育児休業により不就労期間が生じたことを理由に昇格試験の受験機会を与えられませんでした。
この事件は、原告である労働者が法人に対して、職能給の不昇給及び昇格試験を受けさせなかったことが育児介護休業法に違反する不利益取扱いにあたると主張して損害賠償請求した事案となります。
裁判所は、職能給の不昇給について、1年のうち3か月の育児休業により、他の9か月の就労状況いかんにかかわらず、職能給を昇給させないというものであり、休業期間を超える期間を職能給昇給の審査対象から除外し、休業期間中の不就労の限度を超えて育児休業者に不利益を課すものであり、休業法10条に禁止する不利益取扱いに当たるとし、また公序に反し違法無効であるとし賃金差額の損害を認めました。
昇格試験を受けさせなかったことも不法行為に当たるとして、慰謝料15万円を認めました。
トラブル回避のために事業主が取るべき対応について
育児・介護休業法が改正され、事業主が実施すべき対応事項についてご紹介します。
書面による明確な運用ルールの整備
育児・介護休業法が改正に伴う就業規則改定後の育児休業や短時間勤務利用者の評価、処遇、復職後の配置などについて、事前に運用ルールを明文化し、従業員と共有しておくことが重要です。
本人の同意を得た配置転換や業務内容の調整
育児との両立支援の観点から業務を変更する場合でも、本人の希望や事情を十分に考慮し、合理的な範囲で同意を得たうえで行う必要があります。
人事評価基準の透明化
人事評価が不公平と感じられないよう、評価制度を明確化し、評価項目に「育休取得の有無」といった要素を含めないよう徹底します。
トラブルが起きた場合は弁護士への相談が重要
法律の文言だけでは判断が難しいケースも多く、事業主として適切に対応したつもりでも、裁判で違法と判断されることがあります。
例えば、以下のような状況に直面した場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
- 育児休業取得予定者に対して部署異動や契約変更を検討している
- 短時間勤務者の給与や評価について、基準の策定に悩んでいる
- 育児関連制度の運用をめぐって労使間で意見が分かれている
弁護士は、事業主の方針と法令との適合性を確認し、将来的な訴訟リスクを未然に防ぐ助言を行うことができます。
また、労働局や裁判所への対応が必要になった場合にも、事業主側の代理人として交渉・訴訟対応にあたることが可能です。
企業法務のご相談は、弁護士法人シーライトまで
育児休業や短時間勤務制度の利用は、労働者の権利であり、事業主にはこれを適切に受け入れ、尊重する責務があります。
一方で、事業主としての業務運営との調和も求められるため、慎重なバランス感覚が求められます。
処遇の変更を行う際には、「本人の事情」「事業主の事情」「法律の趣旨」の三者を総合的に見たうえでの判断が必要です。
もし、労務に関するご相談や具体的な対応についてご不明な点がございましたら、弁護士法人シーライトまでお問い合わせください。
弁護士 阿部 貴之
最新記事 by 弁護士 阿部 貴之 (全て見る)
- 育児休業者の処遇の変更は違法? 許されるケース・NG事例を解説 - 2025年9月22日
- 痴漢行為で逮捕された場合、懲戒処分の対象となるのか? - 2025年7月25日
- セクハラ問題においてどのような処分が妥当なのか? ~懲戒処分は妥当か否か~ - 2025年3月3日
その他各種労働問題に関するその他の記事はこちら
- 採用内定の法的性質と内定取消しについて
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 継続雇用制度
- 在籍出向について
- 休職の仕組み
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 退職勧奨
- 同一労働同一賃金に向けた当事務所のサポートについて
- 同一労働同一賃金施行後の対応手順
- 同一労働同一賃金への対応ができなかった場合に生じる不利益
- 同一労働・同一賃金のメリット・デメリット
- 日本と海外との同一労働・同一賃金に対する考え方
- 同一労働同一賃金に関連した主たる法律の改正について
- 同一労働同一賃金とは
労働時間管理に関するその他の記事はこちら
弁護士コラムに関するその他の記事はこちら
- 定期健康診断や制服に着替える時間は給料を払わなくてもよい?
- 私的チャットの時間についても支払ってしまった給料は取り返せないのか?
- 痴漢行為で逮捕された場合、懲戒処分の対象となるのか?
- 飲酒運転と懲戒処分
- 採用内定の法的性質と内定取消しについて
- セクハラ問題においてどのような処分が妥当なのか? ~懲戒処分は妥当か否か~
- 通勤手当の不正受給と懲戒処分について
- 年次有給休暇の時季変更権って何?
- 割印って何のために押すの?割印の意味や契印との違い等について解説
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 長時間労働を指摘されるパターンと対策
- 事業場外労働時間制と専門型裁量労働制の「みなし労働時間制度」について
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 不当解雇と言われトラブルになった場合の解雇の撤回について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 普通解雇・懲戒解雇どちらを選ぶべき?懲戒解雇がお勧めできない3つの理由
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 労働基準監督署による調査や是正勧告への対処方法
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- ストレスチェック制度について
- うつなどメンタル不調従業員との雇用契約は解消できるか
- 会社は健康診断の受診拒否や再検査を怠る従業員を懲戒処分できるか?
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 労基署に最低賃金法違反の指摘を受けないよう気を付けるべきこととは?
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 業務上労災にあった従業員の解雇制限
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 残業代請求~名ばかり管理職とは?
- 副業・兼業の導入
- 自己都合退職の退職金
- 退職勧奨
- パートの有給休暇・有給付与義務について