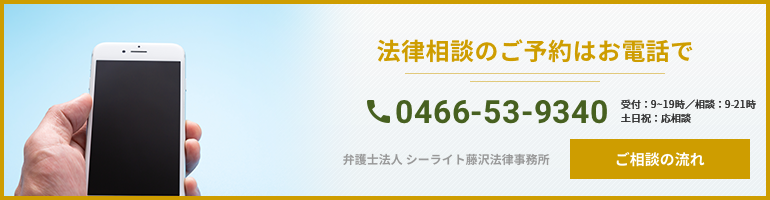採用内定の法的性質と内定取消しについて

年度末が近づいてきましたが、この記事をご覧になっている経営者の皆様は、新たに従業員となる方に内定を出される機会も多くあるかと思います。ただ、内定を出したはいいけれど、「やっぱりあの人を内定とするべきではなかった・・・」、「内定後に問題があることが発覚したけど、内定を取り消すことはできないかな?」などと思われたことはないでしょうか?
この記事では、採用内定の法的性質と内定取消しについて解説いたします。今後の従業員の採用活動にあたって、ぜひ参考にしてください。
Contents
1.内定とは?
まず、(採用)内定とは、一般的には、企業から内定者に内定通知書を出し、それに対して内定者が誓約書等を提出することで、採用の合意がなされた状態をいいます。
これを法的に言うと、採用が内定すると、入社予定日を就労の始期として、内定取消事由が生じた場合に企業が解約できる権利がある「始期付解約権留保付労働契約」が、企業と内定者との間で成立したと考えられています。
つまり、内定となった段階で、企業と内定者との間には労働契約がすでに成立していて、企業は自由に内定取り消しをすることはできない、ということになります。
2.内定取消しができる場合とは?
では、内定取消しは、具体的にどのような場合ならできるのでしょうか?
判例によると、「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」と判断されています(最二小判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁)。
具体的には、以下のような場合には内定取消しができると考えられます。
- 提出書類に重大な虚偽記載がある場合
- 大学等を卒業できなかった場合
- 就労までに必要な資格等を取得できなかった場合
- 業務に重大な支障が生じる健康上の問題があることが発覚した場合
- 刑事事件を起こした場合
- 内定通知書や誓約書等で定めた内定取消事由に該当した場合
(ただし、内定取消事由が客観的に合理的で社会通念上相当なものであることが前提) - 企業が経営難で、整理解雇の要件を充たす場合
3.内定取消しの届出と企業名公表について
企業が内定取消しを行うにあたっては、以下の点に留意する必要があります。
(1)企業が、新規学卒者の内定を取り消す場合には、事前にハローワークに通知をする必要があります(職業安定法施行規則35条2項2号)。
(2)内定取消しの内容が以下の事由のいずれかに該当する場合には、厚生労働省のWEBサイトで企業名や取消しの内容が公表されることがあります(職業安定法施行規則17条の4、平21.1.19厚生労働省告示第5号)。
- 2年度以上連続して行われたもの
- 同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
- 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等に鑑み、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの
- 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
- 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
- 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
4.内定者からの内定辞退について
雇用期間を定めていない場合には、内定者は内定辞退をいつでもすることができ、内定辞退の申し入れから2週間が経過すれば退職できます(民法627条1項)。
経営者の皆様の中には、採用選考の費用をかけて、他の候補者をお断りしていたにもかかわらず内定辞退をされてしまうと多大な損失を被ってしまうため、「内定辞退者に対して損害賠償請求ができないか?」とお考えになる方がいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、「内定辞退の申し入れが、著しく…信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、…債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う」と判断している裁判例(東京地判平成24年12月28日労経速2175号3頁)があることから、内定辞退者に対する損害賠償請求が認められるケースはほとんどないと考えられます。
弁護士法人シーライトでは、顧問契約を締結していただいた企業様の労務問題や問題社員への対応に関するアドバイス等にも力を入れて取り組んでおります。採用内定に限らず、日頃行っている人事労務管理にご不安があるという方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 塩谷 恭平
最新記事 by 弁護士 塩谷 恭平 (全て見る)
- 採用内定の法的性質と内定取消しについて - 2025年3月27日
- 年次有給休暇の時季変更権って何? - 2025年1月23日
- 割印って何のために押すの?割印の意味や契印との違い等について解説 - 2024年12月11日
その他各種労働問題に関するその他の記事はこちら
- 育児休業者の処遇の変更は違法? 許されるケース・NG事例を解説
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 継続雇用制度
- 在籍出向について
- 休職の仕組み
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 退職勧奨
- 同一労働同一賃金に向けた当事務所のサポートについて
- 同一労働同一賃金施行後の対応手順
- 同一労働同一賃金への対応ができなかった場合に生じる不利益
- 同一労働・同一賃金のメリット・デメリット
- 日本と海外との同一労働・同一賃金に対する考え方
- 同一労働同一賃金に関連した主たる法律の改正について
- 同一労働同一賃金とは
弁護士コラムに関するその他の記事はこちら
- 定期健康診断や制服に着替える時間は給料を払わなくてもよい?
- 私的チャットの時間についても支払ってしまった給料は取り返せないのか?
- 育児休業者の処遇の変更は違法? 許されるケース・NG事例を解説
- 痴漢行為で逮捕された場合、懲戒処分の対象となるのか?
- 飲酒運転と懲戒処分
- セクハラ問題においてどのような処分が妥当なのか? ~懲戒処分は妥当か否か~
- 通勤手当の不正受給と懲戒処分について
- 年次有給休暇の時季変更権って何?
- 割印って何のために押すの?割印の意味や契印との違い等について解説
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 長時間労働を指摘されるパターンと対策
- 事業場外労働時間制と専門型裁量労働制の「みなし労働時間制度」について
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 不当解雇と言われトラブルになった場合の解雇の撤回について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 普通解雇・懲戒解雇どちらを選ぶべき?懲戒解雇がお勧めできない3つの理由
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 労働基準監督署による調査や是正勧告への対処方法
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- ストレスチェック制度について
- うつなどメンタル不調従業員との雇用契約は解消できるか
- 会社は健康診断の受診拒否や再検査を怠る従業員を懲戒処分できるか?
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 労基署に最低賃金法違反の指摘を受けないよう気を付けるべきこととは?
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 業務上労災にあった従業員の解雇制限
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 残業代請求~名ばかり管理職とは?
- 副業・兼業の導入
- 自己都合退職の退職金
- 退職勧奨
- パートの有給休暇・有給付与義務について