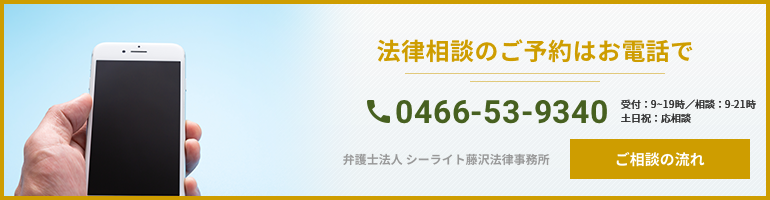私的チャットの時間についても支払ってしまった給料は取り返せないのか?
昨今、自宅でのリモートワークやスマートフォンの普及により、社用端末や業務用メールアドレスをオフィスの外でも利用する従業員が、以前よりも増えたかと思います。
仕事をするための場所やツールが増えたことは、非常に便利であり、仕事の促進を図れるというメリットがある一方で、社用端末や業務用メールアドレスを従業員が、私的目的で利用するリスクも上がり、どのように管理すればよいのかという問題も指摘されます。
労働時間中に行われる社用端末等の私的利用の問題点は、会社の情報漏洩やセキュリティリスクの問題だけではなく、労働時間をどのように扱うかという問題も発生します。
労働時間内における社用端末等の私的利用は、従業員が業務に従事しているといえるのか否か、私的利用を行っている時間の給与の支払いは、発生するのか否かという労務管理上の問題が起こります。
だからといって、社用端末等の私的利用をすべて禁止した場合、従業員がプライベートで緊急を要する場合にも、利用は認められないのかという問題や労働時間内は、私的利用をしているかどうかを常時監視することで、従業員のプライバシーを侵害する可能性があるのではないかという法的問題も起こり得ます。
今回は、労働時間と給料との関係について、具体例を交えながら紹介していきたいと思います。
Contents
ドリームエクスチェンジ事件について
平成28年の裁判例になりますが、業務中の過度な私的チャットの利用が、職務専念義務違反に該当するとして、懲戒解雇された事件について、東京地裁は、懲戒解雇事由に相当するが、費やした時間は労働時間とみなされるという判決(平成28年12月28日の判決)を出しました。
事案の内容
①本訴事件
原告である従業員は、約7ヶ月の間、業務中に社内のパソコンを使い、1日当たり300回以上、時間に換算して2時間程度、業務と無関係のチャットをしていたり、顧客情報の社外持ち出しに関与していたりしたとして平成26年7月8日付けで懲戒解雇(予備的に普通解雇)になったことが無効であると主張し、また、従業員の退職は、同年8月11日付けであり、労働契約に基づき、未払賃金等、遅延損害金、時間外労働に対する割増賃金、遅延損害金の支払いを求める事案でした。
② 反訴事件
その原告である従業員の訴えに対し、会社側は、業務中における私的チャット時間を労働時間から控除すると支払った給与が過払いであるとのことで、不当利得返還請求権に基づいて、既払給与15万8821円の返還を求めました。
また、従業員が社内のチャットにおいて会社に対する信用毀損行為をしたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、300万円と遅延損害金の支払いを求めました。
この事案は、懲戒解雇と支払い済み給与の返還が論点となりました。
結論として、①については、懲戒解雇が認められました。
これは、問題従業員が、当初チャットのやり取り全部を否定していたことや反省の態度が全く見られなかったことから、会社による注意指導を通じての業務態度の改善が困難とみられたためです。
そして、この私的チャットの内容が、顧客情報の流出につながりかねないものであったり、会社が倒産するという事実の摘示により会社の信用及び名誉が毀損されるものであったり、社内の人物に対する誹謗中傷などであったりしたため、社内で許される私語の範囲を逸脱したものであり、職務専念義務に違反するものと判断され、懲戒解雇は有効とされました。
しかし、②については、支払い済み給与の返還が認められませんでした。そして、会社側は、従業員に対して未払残業代の235万1993円と遅延損害金の支払いを命じられました。
既払い給与の返還が認められなかった理由としては、下記の点が挙げられます。
- 私的チャットが従業員同士で行われたものであること
- 業務に無関係なチャットと業務に無関係とまでは言えないチャットとが混然一体となっている面もあって業務に無関係な私的チャットを行っていた時間だけ切り出すことが困難なこと
- あくまで職場での自席にて行われたものなので会社の指揮命令下にあった時間での行動であること
その上で、会社としては業務連絡に用いられている社内チャットの運用が適正になされるよう適切に業務命令権を行使できたのにこれを行使しなかったのだからこういう結論とせざるをえないという趣旨の判示がされています。
私的チャットに関する裁判例が示す労働時間の考え方
労働時間内の私的チャットは、ノーワーク・ノーペイの原則との関係で問題が生じます。しかし会社は、業務連絡に用いる社内チャットの運用が適正になされるように、適切な管理をすることができたにもかかわらず、これを行わなかったことが問題として存在し、結果、今回の事態が起きたと言わざるを得ないとされました。
そして、私的チャットと業務遂行のためのチャットが渾然している状態のため、私的チャットの時間だけを特定することが難しいことも指摘されています。
さらに、私的チャットを行っている従業員の残業について、会社が異議を述べていない点が、会社の黙示の指揮命令であると判断され、その指揮命令下でなされた残業として、労働時間に当たるとされました。
労働者の保護に傾きすぎているように感じる裁判例ですが、現実的には私的チャットと業務的なチャットの時間とを切り分けることが非常に難しいため、日頃の労務管理が大切であるということが反映された結論とも考えられます。
従業員の私的チャットのモニタリングは可能?
では、上記のような労働時間内の、私的チャットを防ぐために、会社側の従業員のメールを監視(モニタリング)することは、問題なのでしょうか?会社としては、労務管理上、従業員が業務に誠実に取り組んでいるかを確認する必要があります。
しかし、従業員にはプライバシー権があり、これに対する配慮も必要となります。では、私的チャットのモニタリングが許されるケースとはどのようなケースなのかについても紹介します。
F社Z事業部事件について
会社のコンピューターネットワークシステムを使った社員の私用メールの使用者による監視についての判断として先例となる裁判例がF社Z事業部事件(東京地裁平成13年12月3日判決)です。
事件の内容
Z事業部の事業部長であった男性社員とZ事業部の女性社員の間に起こった問題になります。この男性社員の行動について、女性社員が会社のコンピューターネットワークシステムを使い、自身の夫へ批判的メールを送信するつもりが、誤って男性社員にメールを送信してしまいます。
このメールを機に、男性社員は女性社員の会社のコンピューターネットワークシステムを使った電子メールを監視しはじめるようになりました。女性社員がパスワードを変更した後も、男性社員は、会社のシステム管理者に女性社員宛の電子メールを自分に転送するよう依頼し、監視し続けました。そのため、女性社員が私的な電子メールを女性社員の許可なく閲覧したとして、不法行為に基づく損害賠償請求をしました。
裁判の判決に見るモニタリングとプライバシー権の問題
東京地裁は、男性社員による女性社員の私的メールのモニタリングについては、その監視行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したものであったとまではいえず、女性社員らが主張する損害賠償に値する重大なプライバシー侵害を受けたとはいえないと判断しました。
それでは、このF社Z事業部事件の判決から企業が従業員の私的チャットのモニタリングを行って良い場合とはどのような場合なのかを考えていきます。
従業員の私的チャットについて
従業員の社用端末による私用メールは、就業規則等で私用メールを明確に禁止していない場合、会社における職務の遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものについて、日常の社会生活を営む上で通常必要な連絡は許容されるものと判断されました。
つまり、従業員が会社から貸与されたパソコンやネットワークを使って、労働時間内に私的なメール(チャット)を送信したとしてもそれだけでは、職務専念義務や企業秩序義務に違反するわけではなく、責任追及はされないということになります。
会社によるモニタリングについて
プライバシー権の侵害となるのは、監視の目的・手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較考量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱して監視がなされた場合に限るとしています。
たとえば、職務上従業員の電子メールの私的使用を監視するような責任ある立場にない者が監視した場合、あるいは、責任ある立場にある者でも、これを監視する職務上の合理的必要性が全くないのに専ら個人的な好奇心等から監視した場合、あるいは、社内の管理部署その他の社内の第三者に対して監視の事実を秘匿したまま個人の恣意に基づく手段方法により監視した場合などについては、プライバシー権侵害になるとしました。
そして、今回の男性社員の監視行為に照らしあわせると、社会通念上相当な逸脱があったとは言えないとされました。
続けて、従業員が社内ネットワークシステムを用いて電子メールを私的に使用する場合に期待しうるプライバシーの保護の範囲は、通常の電話装置における場合よりも相当程度低減されることを甘受すべきとしました。
これは、従業員が社内のネットワークを使って電子メールを利用している以上、プライバシー権への期待は比較的低いとされたということです。つまり、私的メール(チャット)のモニタリングについて、事案ごと総合的に判断し、社会通念上相当といえるかによって判断され、逸脱しない場合には、会社は監視をできるとしました。
ただし、私的メール(チャット)について、プライバシー権は認め、社会通念上相当な範囲を逸脱した場合には、社内メールのモニタリングがプライバシー権侵害として違法になりうるということも明らかにしました。
社内規定の整備と従業員への周知
従業員による労働時間内における私的チャットの問題と会社のモニタリングに関する問題が起きないためにも、社内のルールをしっかりと作成し、従業員へ分かりやすい周知を行うことが大切になります。
従業員の過度な私的チャットを防ぐために、モニタリングを行う場合、電子メール使用規程等でモニタリングを行う場合があることを社内規定で定めることはしなければいけません。そして、モニタリングの実施に関する責任者とその権限についても、ネットワーク利用規定などで従業員へ分かりやすく周知する必要があります。前述のF社Z事業部事件は、会社による私的メールの監視可能性についても社員に告知されていない事案でした。会社は、しっかりとモニタリングの目的を立証可能なものにしておくこと、監視の手段、様態についても社会通念上相当と判断されるように、就業規則でルールを明確にしておくことが重要です。
労務問題は弁護士法人シーライトへご相談ください
私的チャットに関する問題では、労働契約・就業規則・懲戒規定の適用が問題になります。労務問題に詳しい弁護士は、懲戒理由や証拠の妥当性を法的に精査し、過去の裁判例を踏まえたうえで、バランスの取れた処分案を提案します。
また、従業員による解雇無効や損害賠償請求が起きた場合でも、弁護士が対応していくためリスク回避がしやすくなります。私的チャットに関する労務問題を含め様々な労務問題に関し、弁護士を活用することで、法的に正当かつ社内外の理解を得られる対応が実現できます。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人シーライト
最新記事 by 弁護士法人シーライト (全て見る)
- 年末年始休業のお知らせ - 2025年12月17日
- 【メルマガ会員先行公開】定期健康診断や制服に着替える時間は給料を払わなくてもよい? - 2025年12月5日
- 私的チャットの時間についても支払ってしまった給料は取り返せないのか? - 2025年11月25日
問題社員対応に関するその他の記事はこちら
- 痴漢行為で逮捕された場合、懲戒処分の対象となるのか?
- 飲酒運転と懲戒処分
- セクハラ問題においてどのような処分が妥当なのか? ~懲戒処分は妥当か否か~
- 通勤手当の不正受給と懲戒処分について
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 2000万以上の横領被害を1か月半でスピード解決した事案
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
弁護士コラムに関するその他の記事はこちら
- 育児休業者の処遇の変更は違法? 許されるケース・NG事例を解説
- 痴漢行為で逮捕された場合、懲戒処分の対象となるのか?
- 飲酒運転と懲戒処分
- 採用内定の法的性質と内定取消しについて
- セクハラ問題においてどのような処分が妥当なのか? ~懲戒処分は妥当か否か~
- 通勤手当の不正受給と懲戒処分について
- 年次有給休暇の時季変更権って何?
- 割印って何のために押すの?割印の意味や契印との違い等について解説
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 長時間労働を指摘されるパターンと対策
- 事業場外労働時間制と専門型裁量労働制の「みなし労働時間制度」について
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 不当解雇と言われトラブルになった場合の解雇の撤回について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 普通解雇・懲戒解雇どちらを選ぶべき?懲戒解雇がお勧めできない3つの理由
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 労働基準監督署による調査や是正勧告への対処方法
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- ストレスチェック制度について
- うつなどメンタル不調従業員との雇用契約は解消できるか
- 会社は健康診断の受診拒否や再検査を怠る従業員を懲戒処分できるか?
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 労基署に最低賃金法違反の指摘を受けないよう気を付けるべきこととは?
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 業務上労災にあった従業員の解雇制限
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 残業代請求~名ばかり管理職とは?
- 副業・兼業の導入
- 自己都合退職の退職金
- 退職勧奨
- パートの有給休暇・有給付与義務について